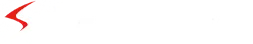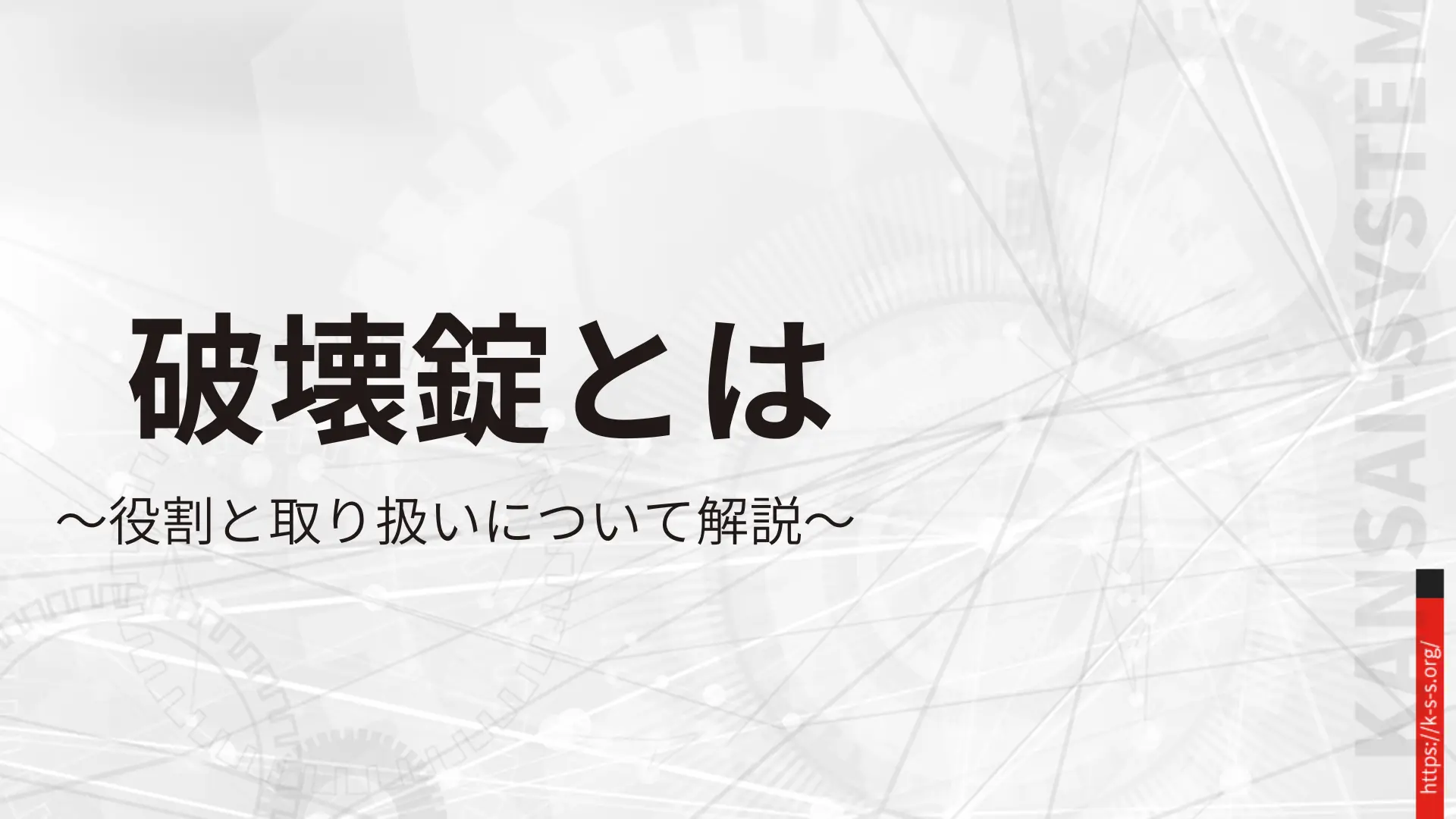破壊錠は、非常時に私たちの安全を確保するために不可欠な鍵です。
火災などの緊急時、避難口が施錠されていては逃げ遅れる危険があるため、消防法でも安全な避難経路の確保が求められています。
マンション等の避難口にあるアクリルカバー付きの鍵がそれにあたります。
この記事では、普段は防犯性を保ちつつ、非常時だけは鍵なしで解錠できる破壊錠の仕組みや設置基準、そして万が一の際の正しい開け方までを詳しく解説します。
破壊錠とは?仕組みと種類

破壊錠(はかいじょう)とは、火災や地震といった非常時に、鍵を持っていなくても屋内から手動で解錠できる「非常錠」のことです。
マンションやビルの屋上、非常階段といった避難口に設置されます。
その目的は、日常的な部外者の侵入を防ぐ「防犯性」と、緊急時に人々が安全に逃げられる「避難経路の確保」を両立させることにあります。
基本的な構造は、主に3つの部品で成り立っています。
- キー(鍵)
- アクリルカバー
- ツマミ(サムターン)
| 部品名 | 説明 |
| キー(鍵) | 平常時に建物の管理者が施錠・解錠に使う通常の鍵(シリンダー)です。 |
| アクリルカバー | 非常用のツマミを保護する透明なカバー。誤操作を防ぎます。 |
| ツマミ(サムターン) | カバーの内部にある非常用のつまみ。これを回すことで、鍵がなくても強制的に解錠できます。 |
種類は主に、カバーを叩き割る「割るタイプ」と、手で外せる「割らないタイプ」に分かれます。「割るタイプ」は一度使うとカバーの交換が必要ですが、緊急性が一目でわかるのが利点です。
一方、「割らないタイプ」は誤って操作しても元に戻せるため、点検時などに便利です。
破壊錠が求められる理由
なぜ破壊錠が必要なのでしょうか。その根拠は、国の消防法および各自治体の火災予防条例にあります。
これらの法律は、火災時に一人でも多くの人が安全に避難できる環境を義務付けています。
特に重要なのが、避難口の管理です。緑色の避難口誘導灯が示す先の扉が施錠されていては、逃げ場を失い大惨事につながります。
この最悪の事態を防ぐため、条例では避難口のあり方が厳しく定められています。
例えば、大阪市火災予防条例第54条には「屋内からかぎを用いることなく、かつ、容易に解錠し、開放できるもの」と明記されています。
参考:https://www.eonet.ne.jp/~fire119/html/jourei.html
この要件を満たしつつ、防犯性を確保する現実的な解決策として、消防署の立入検査では破壊錠の設置が指導されるのです。
非常時の正しい開け方
万が一の際は、慌てずに以下の手順で操作してください。
ステップ1:アクリルカバーを外す
まず、ドアノブ付近にある破壊錠本体を見つけます。そこにある透明なアクリルカバーを外してください。
「割るタイプ」の場合はカバーの中央部を手のひらなどで強く押し込んで割ります。
「割らないタイプ」はカバーの縁を持ち、手前に引くかスライドさせて外します。どちらも特殊な道具は不要です。
ステップ2:ツマミを回して解錠
カバーが外れると、中に赤いツマミやレバー(非常用サムターン)が現れます。
多くの場合、回す方向が矢印で示されています。その指示に従ってツマミを回すと「ガチャン」という手応えがあり、解錠されます。
あとはドアノブを操作して扉を開き、安全に避難してください。
設置・改修工事の費用と流れ
消防署から避難口の施錠について指導を受けた場合、速やかな改修工事が求められます。専門的な施工が必要なため、信頼できる業者への依頼が基本となります。
工事の流れは、一般的に以下の通りです。
- 現地調査・消防署への相談:業者がドアの状態を確認し、改修内容を所轄の消防署に事前相談します。
- 見積もり・機種選定:調査結果に基づき、最適な機種で見積もりが提示されます。
- 施工:既存の鍵を外し、必要ならドアを加工して破壊錠を設置します。
工事期間は1箇所あたり数時間から半日程度が目安です。費用相場は、本体価格と工賃を合わせて30,000円〜70,000円程度です。業者を選ぶ際は、料金体系の明確さ、消防設備に関する施工実績、そしてアフターフォローの有無を確認し、複数の業者から見積もりを取ることを推奨します。
「破壊錠」と「破錠」の違いに注意
非常によく似た言葉ですが、意味は全く異なります。
- 破壊錠(ハカイジョウ):この記事で解説してきた、消防設備としての製品名です。
- 破錠(ハジョウ):鍵を紛失した際などに、鍵屋がドリルでシリンダーを物理的に壊して開ける技術・作業を指します。
緊急時に混同しないよう注意しましょう。
まとめ
破壊錠は、日常の防犯性と非常時の安全な避難経路を両立させる、命を守るための重要な設備です。
その仕組みや使い方を正しく理解し、消防法や条例の基準を満たすため、必要に応じて専門業者へ相談し、設置・改修を行いましょう。