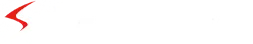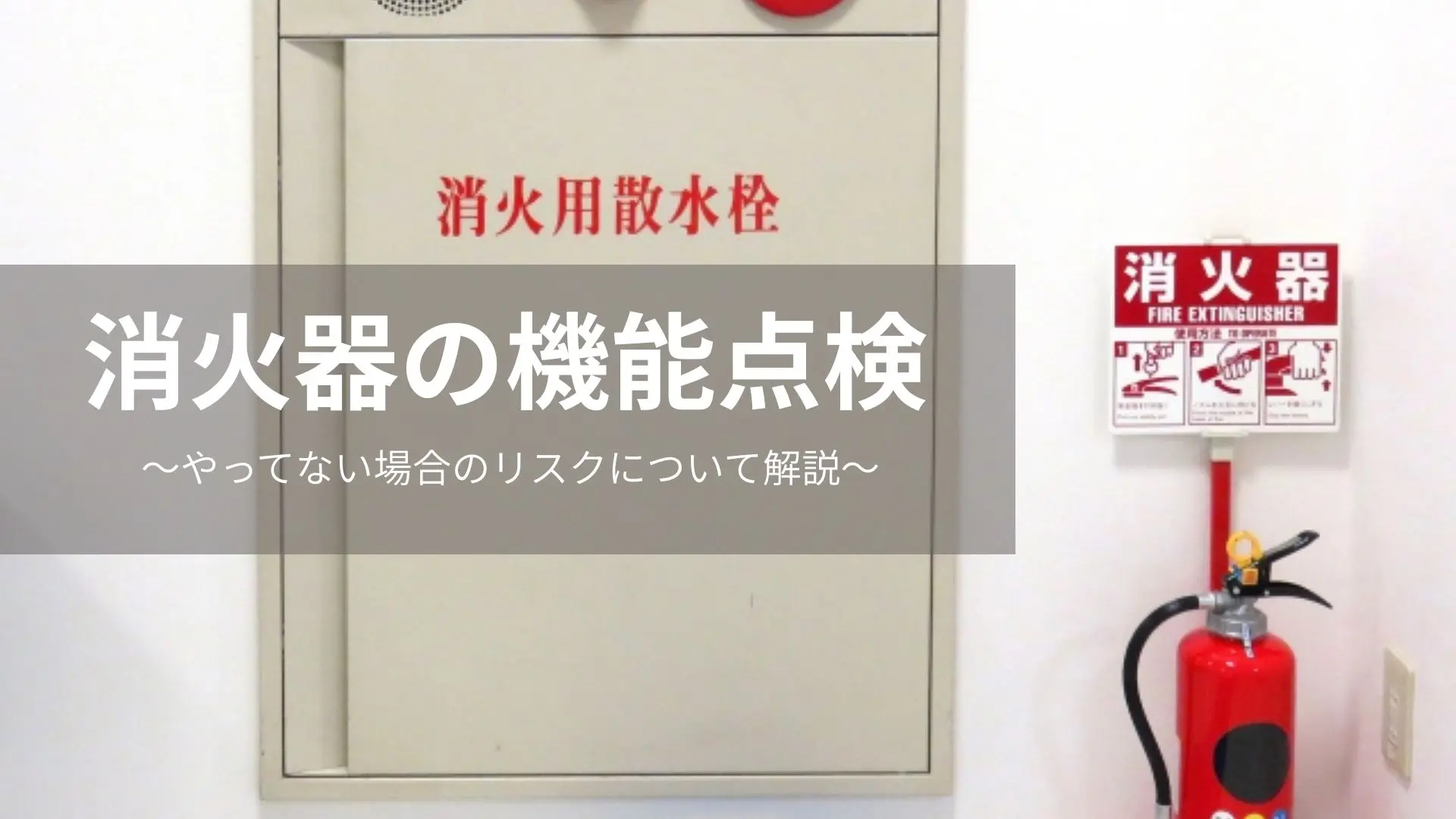「うちのビルの消火器、そういえば機能点検ってやったことないかも…」「点検は費用がかかるし、本当に必要なの?」
建物の所有者や管理者の方なら、一度はこんな疑問を抱いたことがあるかもしれません。特に、日常的に使うものではない消火器のメンテナンスについては、後回しにされがちです。しかし、消火器の機能点検を怠ることは、単に「やっていない」という事実だけでなく、法律違反のリスクや、万が一の火災時に人命を守れないという深刻な事態につながる可能性があります。
この記事では、「消火器の機能点検、やってない」という不安や疑問を抱えるあなたのために、以下の点を徹底的に解説します。
- 機能点検の法的な義務と、やらなかった場合の罰則
- 点検の対象となる消火器の種類と時期
- なぜ「機能点検をやっていない」状況が生まれるのかという業界の背景
- 法令を遵守し、コストも考慮した最も現実的な対応策
この記事を読めば、消火器の機能点検に関する全ての疑問が解消され、あなたの建物に最も適した正しい対応方法が分かります。
消火器の機能点検とは?

まず、混同されがちな「機能点検」と「外観点検」の違いから理解しましょう。これらは点検の目的も内容も全く異なります。
機能点検の定義と目的
機能点検とは、消火器が火災発生時に「実際に正常に作動するか」を確認するための、より専門的な点検です。
製造から一定期間が経過した消火器を対象に、内部の薬剤が固まっていないか、正常に放射できるかといった性能を直接確認します。
この制度は、過去に老朽化した加圧式の消火器が破裂し、死傷者が出た痛ましい事故を背景に導入されました。
そのため、専門的な知識と技術が不可欠であり、消防設備士(乙種第6類)または第1種消防設備点検資格者といった有資格者でなければ実施できません。
外観点検との違い
一方、外観点検は、その名の通り消火器の外観を目視で確認する点検です。容器に錆や腐食、変形がないか、安全栓がしっかりついているか、圧力ゲージの針が正常な範囲を指しているか(蓄圧式の場合)などをチェックします。
外観点検は半年に1回、設置されている全ての消火器に対して実施が義務付けられています。
これに対し、機能点検は製造から一定年数が経過したものが対象となり、外観だけでは分からない内部の状態や性能を確認する、という点が大きな違いです。
| 点検の種類 | 目的 | 頻度 | 対象 |
| 機能点検 | 内部の性能・作動状況の確認 | 製造年から一定期間経過後 | 対象となる消火器 |
| 外観点検 | 容器の変形・腐食・圧力等の確認 | 6ヶ月に1回 | 全ての消火器 |
消火器の機能点検、やらないとどうなる?法的義務と罰則
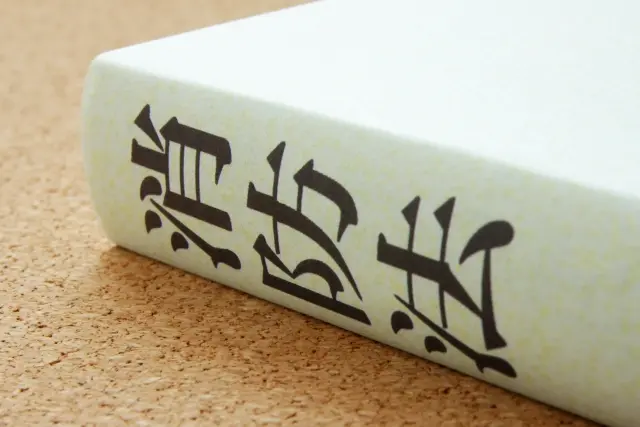
「機能点検が必要なのは分かったけど、もしやっていなかったらどうなるの?」という点が最も気になるところでしょう。結論から言えば、法的な義務であり、罰則も存在します。
消防法に基づく点検義務
消火器の機能点検は、「消防用設備等点検」の一部です。消防法第17条の3の3により、消火器の設置義務がある建物(消防法では「防火対象物」と呼びます)の関係者(所有者・管理者・占有者)に、点検の実施が義務付けられています。
この点検は、6ヶ月ごとに行う「機器点検」の項目に含まれます。
点検結果は定められた様式の点検票に記録し、他の消防用設備の点検結果と合わせて、建物の用途や規模に応じて1年または3年に1度、管轄の消防署長に報告する義務があります。
法令違反のリスクと罰則
もし機能点検が必要な条件に該当するにもかかわらず実施しなかった場合、消防用設備等点検の義務を怠ったとして法令違反に問われる可能性があります。
具体的には、点検を行わなかったり、虚偽の報告をしたり、そもそも報告自体をしなかったりした場合には、消防法第44条に基づき30万円以下の罰金または拘留に処せられる可能性があります。
罰則以上に重要なのが、人命に関わるリスクです。実際に老朽化した消火器の破裂事故は発生しており、人的被害も報告されています。
万が一の火災時に「消火器が使えなかった」では済みません。適切な保守管理は、建物の安全を守るための最低限の責務なのです。
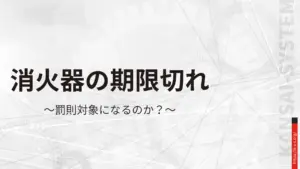
機能点検の対象となる消火器と実施時期

全ての消火器がすぐに機能点検の対象になるわけではありません。消火器の種類と製造年によって、点検を開始する時期が異なります。
加圧式消火器の場合
製造年から3年を経過したものが機能点検の対象です。
加圧式消火器は、本体容器とは別に「加圧用ガス容器(ボンベ)」が内蔵されています。
使用時にレバーを握ると、このボンベが破れて内部に圧力がかかり、薬剤が放出される仕組みです。
平常時は容器内に圧力がかかっていないのが特徴で、設計標準使用期限は製造年から概ね8年~10年とされています。
蓄圧式消火器の場合
製造年から5年を経過したものが機能点検の対象となります。
(※一部メーカーの資料では、法令改正により「製造後6年目から」と案内されているケースもあります。)
蓄圧式消火器は、製造段階で容器本体に窒素ガスなどが封入されており、常に容器内に圧力がかかっている状態です。
本体に必ず圧力ゲージ(指示圧力計)が付いており、針が緑色の範囲にあれば圧力が正常であることを日常的に確認できます。
加圧式に比べて構造的に破裂リスクが低いとされており、現在の主流となっています。設計標準使用期限は製造年から概ね10年です。
抜き取り方式(サンプリング検査)の仕組み
機能点検は、対象となる消火器の全てを分解するわけではありません。「抜き取り方式(サンプリング検査)」という合理的な方法が認められています。
まず、同じ種類、同じ製造年の消火器を一つのグループ(確認ロット)としてまとめます。そして、そのロットの中から一定の割合を抜き取って点検を実施します。具体的な抜き取り率は、以下の通り定められています。
- 内部・薬剤等の確認: 機能点検の対象となるロットの設置総数の10%以上を抜き取る。
- 放射試験: 上記1で抜き取った消火器のうち、さらに50%以上で実際に放射試験を行う。
例えば、同じ種類の蓄圧式消火器が20本あり、全てが機能点検の対象だった場合、まず10%以上にあたる2本以上を抜き取って内部点検を行います。
さらに、その2本のうち50%以上、つまり1本以上で実際に放射して性能を確認する必要がある、ということです。
もし、この抜き取り検査で異常が見つかった場合は、そのロットの全ての消火器を点検する必要が出てくることもあります。
耐圧性能点検(水圧試験)について
機能点検とは別に、製造年から10年を経過した消火器(一部を除く)については、耐圧性能点検(水圧試験)を3年ごとに実施する義務があります。
これは、消火器の容器自体が圧力に耐えられるかどうかを確認する試験で、容器に水圧をかけて変形や漏れがないかを調べます。
この点検も専門性が高く、コストもかかるため、多くの場合は新品への交換が選択されます。
消火器の「機能点検をやってない」の背景と課題
法令で義務付けられているにも関わらず、なぜ「機能点検をやっていない」という状況や、「やる意味がない」といった声が生まれるのでしょうか。
そこには、コストや合理性に関する業界特有の課題が存在します。
コスト問題
特に蓄圧式消火器の機能点検は、コストが大きな課題です。点検のためには一度分解し、薬剤を確認後、再び組み立てて窒素ガスなどを充填する必要があります。
この作業は現場で行うのが難しく、業者が一旦工場へ持ち帰ることがほとんどです。
そのため、点検費用本体に加え、運搬費、点検期間中の代替消火器の設置費用、薬剤の補充費用などがかさみ、結果的に新品の消火器を1本購入するよりも点検費用の方が高額になるケースが多く発生します。
さらに、製造から10年が経過して耐圧性能点検の時期を迎えると、その費用も上乗せされます。こうした背景から、多くの消防設備点検業者は、機能点検の対象時期が来た消火器について、点検ではなく新品への交換を推奨するのが実情です。
コスト面で合理的な判断と言えるでしょう。
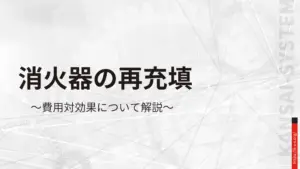
蓄圧式における分解点検の必要性への疑問
そもそも機能点検の制度は、老朽化した加圧式消火器の破裂事故がきっかけで強化された経緯があります。
しかし、前述の通り、現在の主流である蓄圧式は構造的に破裂リスクが低く、圧力ゲージで内部圧力をいつでも確認できます。
そのため、業界内では「リスクの低い蓄圧式に対して、高コストな分解点検を義務付けるのは本当に合理的か?」という疑問の声が根強くあります。
点検のために一度分解し、再組立てを行うことが、かえって製品の密封性を損なうリスクにつながるという見方さえあるのです。
正しい対応と今後の展望
では、建物の管理者として、私たちはどうすればよいのでしょうか。法令を遵守し、かつ現実的な対応を取るための選択肢を整理します。
「機能点検済」と報告するための選択肢
現状、法令に則って適切に「機能点検済み」として報告するためには、実質的に以下の2つの選択肢があります。
- 法令通り、抜き取り方式で機能点検を実施する
抜き取り検査を行い、放射試験で使った消火器は廃棄して新品に補充する方法です。コストはかかりますが、最も厳密な方法です。 - 機能点検の開始時期に合わせて、対象の消火器を全数新品に交換する
これが最も現実的かつ多くの現場で採用されている方法です。加圧式なら製造後3年、蓄圧式なら製造後5年(または6年目)のタイミングで、点検対象となるロットを全て新品に買い替えます。これにより、点検費用の問題をクリアしつつ、常に新しい消火器が設置されているという安全上のメリットも得られます。
どちらを選択するにせよ、現状の課題や選択肢について詳しく説明し、あなたの建物にとって最適な提案をしてくれる信頼できる専門業者を選ぶことが何よりも重要です。
メンテナンスフリー規格や法令改正への期待
業界では、現場の実態に合わせたルールの改正が長年望まれています。より安全性の高い蓄圧式消火器への完全移行や、点検の手間を省ける「メンテナンスフリー」を謳った新しい規格の製品の普及などが進めば、将来的には状況が変わる可能性があります。
消防設備士の本来の使命は「火災による被害を軽減すること」です。形骸化したルールを守るだけでなく、法令遵守と持続可能な業務を両立させるために、業界全体で知恵を絞っていく必要があります。
まとめ
最後に、この記事の要点をまとめます。
- 消火器の機能点検は消防法で定められた義務であり、怠ると**罰則(30万円以下の罰金または拘留)**の対象となる可能性があります。
- 点検対象は、加圧式が製造後3年、**蓄圧式が製造後5年(または6年目から)**で、抜き取り方式で実施されます。
- しかし、点検には高額なコストがかかるため、現実的には機能点検の時期に合わせて新品に交換することが最も合理的で一般的な選択肢となっています。
- 不正な報告は絶対に避け、万が一の事態に備えなければなりません。
消火器は、あなたとあなたの建物を守るための最も身近な消防設備です。その価値は、火災が起きた時に初めて発揮されます。「やってない」状態を放置せず、この記事を参考に信頼できる業者へ相談し、法令を遵守した上で、最も現実的で安全な対応を選択してください。