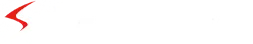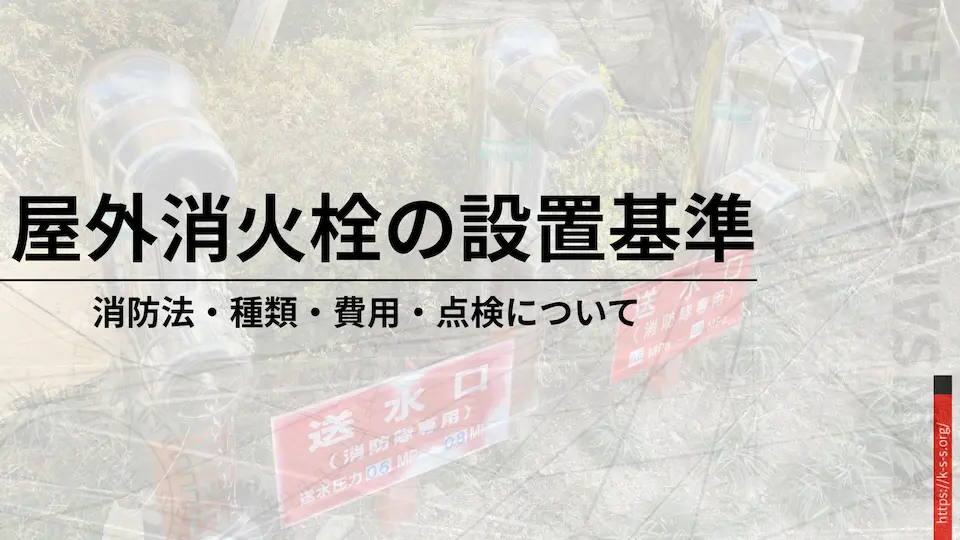「自社の工場や倉庫に屋外消火栓は必要なのだろうか?」「消防法ではどのような基準が定められているの?」
大規模な建物や敷地を管理する方にとって、屋外消火栓の設置基準は複雑で分かりにくいものです。
設置には高額な費用がかかるため、本当に義務があるのか、どのような設備を選べばよいのか、正確な情報に基づいて判断したいとお考えでしょう。
この記事では、屋外消火栓の役割から、消防法で定められた詳細な設置基準、設備の種類、導入費用、そして維持管理に不可欠な点検まで、網羅的に解説します。
屋外消火栓とは?
屋外消火栓は、建物の外部から消火活動を行うための設備です。主な目的は、隣接する建物への延焼防止と、大規模火災の鎮圧です。初期消火としても重要な役割を果たします。
特に、1階や2階での火災リスクが高い平屋建ての工場、倉庫、大規模店舗などに設置されます。
屋外消火栓設備は、複数の要素で構成されています。
- 水源(消火水槽など)
- 加圧送水装置(消火ポンプ)
- 配管・弁類
- 消火栓本体
- ホース・ノズル
- 非常電源
火災時には加圧送水装置が起動します。水源から水を汲み上げ、配管を通じて消火栓本体へ送水します。そしてホースとノズルを使って放水する仕組みです。
屋外消火栓の特徴は、防護範囲の広さです。
屋内消火栓の水平距離が25m以下なのに対し、屋外消火栓は40m以下と定められています。これにより、広大な敷地を効率的にカバーできます。
消防法で定められた屋外消火栓の「設置基準」
屋外消火栓の設置義務は、消防法に基づき定められています。具体的な基準は「消防法施行令」に明記されています。特に重要なのが、令第19条(屋外消火栓設備に関する基準)です。
この法令に基づき、建物の構造と床面積によって設置の要否が判断されます。ここでは、具体的な設置基準を解説します。
建物構造・面積に関する基準
設置基準は、建物の燃えにくさ(耐火性能)によって異なります。建物は「耐火建築物」「準耐火建築物(簡易耐火建築物)」「その他の建築物」に分類されます。
それぞれの構造で、「1階」または「1階及び2階部分の床面積の合計」が以下の基準以上となる場合、設置が義務付けられます。
| 建物の種類 | 1階または1階及び2階部分の床面積基準 |
| 耐火建築物 | 9,000平方メートル以上 |
| 準耐火建築物 | 6,000平方メートル以上 |
| その他の建築物 | 3,000平方メートル以上 |
木造などの「その他の建築物」は燃えやすいため、最も厳しい基準が適用されます。
同一敷地内の複数建築物に関する基準
同一敷地内に2つ以上の建築物がある場合、特定の条件下でそれらを「一つの建築物」とみなす規定があります。これは、建物同士が近いと延焼リスクが高まるためです。
具体的には、耐火建築物および準耐火建築物を除いた建築物同士で、外壁間の中心線からの水平距離が以下の範囲にある場合です。
- 1階:3メートル以下
- 2階:5メートル以下
例えば、敷地内に木造倉庫が2棟あり、1階部分が2mの間隔で建っている場合です。この場合、2棟の床面積を合計して設置基準を判断する必要があります。
設置免除となる条件
基準に該当する場合でも、設置が免除されるケースがあります。消防法施行令第19条第4項では、他の高性能な消火設備が設置されている場合の免除条件が定められています。
具体的には、以下の設備が有効範囲内に設置されている場合です。
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
- 動力消防ポンプ設備
これらの設備が、屋外消火栓と同等以上の消火能力を持つと判断される場合に限ります。
屋外消火栓設備の「性能基準」と「表示」のルール
屋外消火栓は、火災時に確実に機能しなければなりません。そのため、消防法では設備の性能に関する技術的な基準も詳細に定められています。
ここでは、ホース接続口の配置、水源、放水性能、そして視認性のルールについて解説します。
ホース接続口の水平距離とホースの長さ
屋外消火栓は、建物の周囲をくまなく防護できるように配置する必要があります。
基準として、建築物の各部分からいずれかのホース接続口までの水平距離が「40メートル以下」でなければなりません。これは、火災現場へ迅速に到達できる範囲を考慮したものです。
また、使用する消防用ホースの長さも重要です。一般的に、屋外消火栓では20mのホースを2本連結して使用します。これにより、40mの範囲内にある火点に対して、有効に放水活動を行うことが可能になります。
水源の水量と放水性能
火災鎮圧には、十分な水量と強力な放水性能が不可欠です。
まず、水源の水量基準です。屋外消火栓の設置個数(同時に使用するのは最大2個まで)に「7立方メートル」を乗じた量以上が必要です。2個設置なら14立方メートル以上の水が求められます。
この水量は、規定の性能で約20分間放水し続けられる量に相当します。
次に、放水性能基準です。すべての屋外消火栓を同時に使用した場合(最大2個)、ノズルの先端で以下の性能を満たす必要があります。
- 放水圧力:0.25MPa(メガパスカル)以上
- 放水量:毎分350リットル以上
この高い性能を維持するために、適切な加圧送水装置の選定が重要です。
非常電源とホース格納箱の設置場所
火災時には停電が発生する可能性があります。停電時でも加圧送水装置(ポンプ)を稼働させるため、非常電源の設置が義務付けられています。
非常電源には、自家発電設備や蓄電池設備などが用いられます。
また、屋外消火栓本体や放水用器具(ホース、ノズルなど)を収納するホース格納箱の設置場所も重要です。
これらは、火災時に迅速に取り出せる場所に設置する必要があります。避難経路や車両の通行を妨げる場所への設置は認められません。
標識と赤い表示灯の設置ルール
屋外消火栓の場所を一目で認識できるよう、視認性を確保するルールがあります。
まず、ホース格納箱には「消火栓」と表示した標識を見やすい位置に設けなければなりません。
さらに、屋外消火栓の位置を示すための赤い灯火(表示灯)の設置も義務付けられています。
表示灯は通常、消火栓本体の直近やホース格納箱の上部に設置されます。一般的には直径60mm以上の円形のものが用いられ、常時点灯させておく必要があります。
【関連記事例】 ・消防設備の表示灯(赤色灯)の基準と役割 ・非常電源(自家発電・蓄電池)の種類と点検ポイント
3つの種類で選ぶ屋外消火栓の特徴
屋外消火栓には、設置環境や用途に応じて主に3つの種類があります。「器具格納式消火栓」「地下式消火栓」「地上式消火栓」です。
それぞれの特徴を理解し、最適なタイプを選ぶことが重要です。
器具格納式消火栓
特徴
赤色の格納箱にホース、ノズル、開閉弁など必要な器具一式が全て収納された一体型です。
「ボックス型」や「オールインワン型」とも呼ばれます。
メリット
器具がまとまっているため、設置スペースの確保や管理が比較的容易です。
設置場所
工場、倉庫、駐車場の壁面沿いなど。
地下式消火栓
特徴
地面の下に設置され、マンホールの蓋の下に本体が格納されているタイプです。
メリット
都市部や交通量の多い場所でも通行の妨げになりません。地中にあるため凍結リスクが低く、外部からの損傷を受けにくい点も特徴です。
注意点
火災時にすぐに使用できるよう、マンホール蓋の上やホース格納箱の前に物を置かないよう注意が必要です。また、開閉弁の深さなどにも基準があります。
地上式消火栓
特徴
地面上に赤色の円柱状(ポール型)で設置され、バルブや接続口が露出している最も一般的なタイプです。
メリット
視認性が高く、素早く発見・使用が可能です。操作も比較的簡単です。
基準
ホース接続口は、操作性を考慮し、地面から0.5メートル以上1.0メートル以下の高さに設置する必要があります。
【関連記事例】 ・器具格納式消火栓のメリットと導入事例 ・寒冷地における消火栓の選び方(地上式・地下式)
屋外消火栓と屋内消火栓の「違い」
屋外消火栓と屋内消火栓は、名前は似ていますが、目的と性能が大きく異なります。最も重要な違いは、「想定される主な使用者」と「放水能力」です。
屋内消火栓は、建物内にいる一般の方が初期消火を行うために設置されています。そのため、誰でも比較的容易に操作できるよう設計されています。
一方、屋外消火栓は、訓練を受けた消防隊員や自衛消防隊員などが、本格的な消火活動や延焼防止を行うために使用します。
この違いは、放水能力に顕著に現れています。
| 項目 | 屋外消火栓 | 屋内消火栓 |
| 主な目的 | 外部からの本格的な消火活動、隣接建物への延焼防止 | 建物内部での初期消火 |
| 想定使用者 | 訓練を受けた消防隊員や自衛消防隊員など | 建物の中にいる一般の建物利用者 |
| 放水能力 | 放水圧力: 0.25MPa以上、放水量: 350L/分以上 | 放水圧力: 0.17MPa以上、放水量: 130L/分以上 |
屋外消火栓の放水量(毎分350L以上)は、屋内消火栓の約2.7倍にもなります。
この高い放水能力ゆえに、操作には大きな反動力が伴います。
そのため、専門的な知識と技術、体力が必要であり、訓練を受けていない一般の方が扱うのは非常に危険です。
【関連記事例】 屋内消火栓の種類(1号・易操作性1号・2号)と使い方 ・自衛消防隊の役割と必要な訓練について
屋外消火栓の設置費用
屋外消火栓の設置には多額の費用がかかります。また、設置後も消防法に基づき、適切な維持管理と定期的な点検が義務付けられています。
ここでは、設置費用の相場と、専門業者による点検の重要性について解説します。
新規設置にかかる費用相場と内訳
屋外消火栓の新規設置費用は、約80万円から1,000万円以上と非常に幅広くなります。これは、建物の規模や構造、既存のインフラ状況によって、必要な設備や工事内容が大きく異なるためです。
主な費用の内訳は以下の通りです。
- 加圧送水装置(ポンプユニット):数十万円〜数百万円
- 水源(消火水槽):設置が必要な場合、数百万円以上
- 消火栓本体・ホース格納箱:1基あたり数万円〜数十万円
- 配管工事費:距離や埋設深度により大きく変動
- 電気工事費:非常電源の設置を含む
- 設計・申請費用
例えば、広大な敷地に新たに大容量の消火水槽や高性能なポンプを導入する場合、総費用は高額になります。
正確な費用を知るには、専門業者による現地調査と見積もりが不可欠です。
定期点検の種類と内容
消防法により、屋外消火栓設備は定期的な点検と、その結果の消防署への報告が義務付けられています。点検には「機器点検」と「総合点検」の2種類があります。
- 機器点検(6ヶ月に1回以上) 設置されている各装置(ポンプ、配管、消火栓本体、ホース格納箱、非常電源等)の外観や設置状況に異常がないかを確認します。また、水源の水位は規定量か、表示灯や標識は適切かなどもチェックします。
- 総合点検(1年に1回以上) 機器点検の内容に加え、実際に屋外消火栓設備を作動させ、総合的な機能を確認します。規定の放水圧力や放水量が出ているか、非常電源は正常に切り替わるかなどをテストします。
寒冷地での点検の注意点と専門業者への依頼
屋外に設置される設備であるため、特に寒冷地では冬季の凍結リスクに注意が必要です。
配管内の水が凍結すると、いざという時に設備が使用不能になります。また、配管が破損する恐れもあります。
そのため、寒冷地では以下のような対策が重要です。
- 不凍栓など、寒冷地仕様の屋外消火栓を採用する。
- 配管にヒーターを巻くなどの凍結防止措置を施す。
点検時には、これらの凍結防止措置が適切に機能しているかの確認も欠かせません。
屋外消火栓の点検には、専門的な知識と技術、専用測定機器が必要です。
そのため、点検は必ず消防設備士などの有資格者が所属する専門業者に依頼しなければなりません。
屋外消火栓に関するよくある質問(FAQ)
屋外消火栓に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 屋外消火栓は一般の人でも操作できますか?
-
基本的に専門的な訓練を受けた消防隊員や自衛消防隊員による操作が推奨されます。 屋外消火栓は非常に高い放水能力を持つため、一般の方が扱うと、ホースの反動で転倒したり、高い水圧で怪我をしたりする危険性があるためです。
- 屋外消火栓の設置が免除されるのはどのような場合ですか
-
消防法施行令第19条第4項に基づき、スプリンクラー設備や泡消火設備など、特定の他の消火設備がその有効範囲内に設置されている場合は、設置が免除されることがあります。詳細は管轄の消防署にご確認ください。
- 屋外消火栓の点検を怠るとどうなりますか?
-
消防法で義務付けられている機器点検(6ヶ月に1回以上)と総合点検(1年に1回以上)を怠ると、法的義務違反となり罰則の対象となる可能性があります。また、火災時に設備が正常に機能せず、甚大な被害が生じるリスクが高まります。
屋外消火栓の設置・点検は関西システムサポートへ
この記事では、屋外消火栓の設置基準、性能、種類、そして費用や点検について詳しく解説しました。
屋外消火栓は、火災から大切な建物を守るために不可欠な設備です。しかし、その設置基準は消防法(消防法施行令第19条)で細かく規定されています。建物の床面積や構造(耐火建築物か否かなど)によって複雑に変化します。
また、地上式、地下式、器具格納式といった多様な種類から最適なものを選定する必要があります。適切な放水圧力と放水量を確保するためにも、専門知識が求められます。
そして何より重要なのは、設置後の適切な維持管理です。定期点検を実施し、常に万全の状態を保つことが法令で義務付けられています。
屋外消火栓の新規設置や定期点検は、専門的な知識と技術を持つ信頼できる専門業者に相談・依頼することが最も確実で安全です。
あなたの建物は、最新の消防法基準を満たしていますか?
屋外消火栓の設置に関するご相談、現状の設備の点検・メンテナンスは、経験豊富な私たち関西システムサポートにお任せください。
専門の消防設備士が、貴社の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。