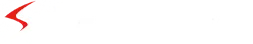「自分のビルに誘導灯は必要なのだろうか?」「設置基準が複雑で、どこから手をつけていいか分からない…」。
建物の安全管理を担当する方にとって、誘導灯に関する悩みは尽きないものです。
万が一の火災時、人々の命を守る生命線となる誘導灯。
誘導灯の設置は消防法で厳しく定められていますが、専門用語が多く、基準も多岐にわたるため、全てを正確に把握するのは困難です。
この記事では、そんなお悩みを解決するため、誘導灯の役割から具体的な設置基準、種類ごとの違い、費用相場、さらには設置が免除されるケースまで、専門家の視点から網羅的に解説します。
最後まで読めば、あなたの建物に最適な安全対策を講じるための、確かな知識が身につくはずです。
誘導灯とは?

誘導灯は、火災や地震などの災害時に、人々を安全な避難経路へと導くための照明設備です。
これは単なる努力義務ではなく、消防法によって設置が厳しく義務付けられています。
結論として、誘導灯は「人命を守るための道しるべ」であり、その設置は建物の安全性を確保する上で不可欠です。
なぜなら、災害発生時には停電が起こり、視界が著しく悪化することが想定されるからです。
特に火災では、煙が充満し、慣れた建物内であっても方向感覚を失いやすくなります。
このような極限状況下で、非常電源によって点灯し続ける誘導灯が、唯一の光の道標となります。
この法的拠点は消防法施行令第26条や消防法施行規則第28条の3で明確に定められており、特定の防火対象物には必ず設置しなければなりません。
誘導灯が活躍するシーン
例えば、大規模な商業施設で火災が発生したとします。
館内は瞬く間に停電し、人々の悲鳴と煙でパニック状態に。しかし、その暗闇の中で緑色に光る誘導灯だけが、冷静に出口の方向を示し続けます。
人々はその光を頼りに、煙を避けながら安全な出口へと向かうことができます。
このように、誘導灯はパニック時における避難行動を冷静にサポートし、一人でも多くの命を救うための重要な役割を担っているのです。
誘導灯の種類とそれぞれの役割

誘導灯にはいくつかの種類があり、設置される場所や目的に応じて使い分けられます。
ここでは主要な種類と、よく混同されがちな「誘導標識」との違いを、表形式で分かりやすく解説します。
| 種類 | 役割 | 特徴 | 主な設置場所 |
| 避難口誘導灯 | 屋内から直接地上へ通じる出入口や避難階段の入口を明確に示す。 | 「非常口」そのものを指し、矢印はない。緑色の背景に白いピクトグラム。表示面の視認性を確保するため、周囲に紛らわしい広告物などを設置することは禁じられている。 | 避難口の直上や、そのすぐ近くの壁面など。 |
| 通路誘導灯 | 廊下や通路を進むべき方向を明示し、人々を避難口まで導く。 | 避難方向を示す緑色の矢印が描かれている。リレー形式で配置され、歩行距離を考慮して設置間隔が定められている。 | 廊下、階段、通路の曲がり角など。 |
| 客席誘導灯 | 暗い客席内で、観客が安全に通路へ移動できるよう足元を照らす。 | 非常時には0.2ルクス以上の明るさを確保することが求められる。矢印はない。 | 客席の通路に面した部分の床面や壁の下部。 |
| 階段通路誘導灯 | 階段の段差や通路の傾斜を明確にし、転倒などの事故を防ぐ。 | 非常時には1ルクス以上の明るさを確保する必要がある。非常灯の役割を兼ねることができる場合もある。 | 階段の踊り場や踏面、傾斜路の壁面など。 |
| 誘導標識 | 誘導灯と同様に、避難口の場所や方向を示す。 | 自ら発光しない標識板。蓄光式誘導標識のように光を蓄えて暗闇で発光するタイプもある。 | 廊下や壁面など、誘導灯に準じた場所。 |
誘導灯の設置基準をわかりやすく解説
誘導灯の設置は、建物の用途や規模によって細かく定められた設置基準に従う必要があります。
ここでは、どのような建物が対象になるのか、そして誘導灯の性能を示すクラス分けについて具体的に解説します。
設置対象となる「防火対象物」
消防法では、誘導灯の設置義務がある建物を「防火対象物」として定めています。
特に、不特定多数の人が利用する施設や、災害時に自力での避難が難しい人がいる施設では、厳しい基準が適用されます。
例えば、地階や無窓階、11階以上の階は、避難が困難であるため、ほとんどの建物で設置が義務付けられています。
| 消防法施行令における区分 | 防火対象物の例 | 避難口誘導灯 設置対象 | 通路誘導灯 設置対象 | 客席誘導灯 設置対象 | 誘導標識 設置対象 |
| (一)項 イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 | 全ての階 | 全ての階 | 全ての階 | 全ての階 |
| (五)項 ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | 地階、無窓階、11階以上の部分 | 地階、無窓階、11階以上の部分 | なし | 全ての階 |
| (六)項 イ | 病院、診療所、助産所 | 全ての階 | 全ての階 | なし | 全ての階 |
| (十六の二)項 | 地下街 | 全ての階 | 全ての階 | (一)項用途部分 | 全ての階 |
誘導灯のクラス(A級・B級・C級)と有効範囲
誘導灯は、その性能によってA級、B級(BH形・BL形)、C級に区分されます。
このクラスは表示面の大きさや明るさによって決まり、避難できる有効範囲(歩行距離)が異なります。
大規模な施設ほど、より遠くからでも視認できる高性能なA級やB級の誘導灯が必要となります。
| 区分 | 表示面の縦寸法(メートル) | 表示面の明るさ(カンデラ) | 有効範囲(歩行距離D) | 備考 |
| 避難口誘導灯 A級 | 0.4以上 | 50以上 | 60m | D=khのk値は150 |
| 避難口誘導灯 B級 | 0.2以上0.4未満 | 10以上 | 20m (BH形) / 30m (BL形) | D=khのk値は100 |
| 通路誘導灯 C級 | 0.1以上0.2未満 | 5以上 | 10m | D=khのk値は50 |
| *有効範囲の計算式: D = kh (D:歩行距離, k:比例定数, h:表示面の縦寸法) |
特定の場所における設置要件
誘導灯は、ただ設置すれば良いわけではありません。
- 避難口誘導灯は「屋内から直接地上へ通ずる出入口」や「直通階段の出入口」など、最終的な避難口となる場所に設置します。
- 通路誘導灯は廊下の「曲がり角」や、避難口誘導灯が見えない場所からその有効範囲内までを補うように設置します。
誘導灯は、原則として常時点灯が義務付けられています。
これにより、いつ災害が起きても確実に機能します。ただし、建物の用途や場所によっては、自動火災報知設備の作動と連動して点灯する方式も認められています。
さらに、大規模な施設や地下街などでは、避難をより効果的に促すため、点滅機能や音声誘導機能が付加された誘導灯の設置が求められる場合があります。
誘導灯の設置が免除される建物
一定の条件を満たす場合には、誘導灯の設置義務が免除されることがあります。
これは、小規模な建物や、避難が容易であると判断される構造の場合に適用されます。
結論として、避難口までの見通しが良く、容易に識別できることが免除の大きなポイントです。
主な免除条件は、居室の各部分から主要な避難口までの歩行距離によって定められています。
| 誘導灯の種類 | 免除される歩行距離(避難階) | 免除される歩行距離(避難階以外の階) |
| 避難口誘導灯 | 20m以下 | 10m以下 |
| 通路誘導灯 | 40m以下 | 30m以下 |
| 誘導標識 | 30m以下 (各部分から) | 30m以下 (各部分から) |
| *注: 上記は主な基準であり、建物の用途や構造によって条件は異なります。 |
国の消防法だけでなく、各地方自治体が定める条例によって、設置基準が追加されたり、逆に緩和されたりする場合があります。
例えば、東京都の「火災予防条例」では、国の基準よりも対象となる建物の範囲が広く設定されているケースがあります。
建物を管轄する地域の消防署に確認することが重要です。
誘導灯設置に関するよくある質問
ここでは、誘導灯の設置や管理において、オーナー様や管理者様からよく寄せられる質問にお答えします。
既存の蛍光灯タイプからのLED化は必須?

結論から言うと、法的な強制力はまだありませんが、LED化は強く推奨されます。
2027年末で多くの蛍光ランプの製造・輸入が禁止されるため、いずれは交換が必要になります。
LED化には、消費電力の大幅な削減、長寿命化によるメンテナンスコストの低減など、多くのメリットがあります。
ただし、交換には初期費用がかかり、既存の配線や非常電源との適合性を確認する必要があります。
設置費用・維持管理費用はどのくらい?
費用は、誘導灯の種類、設置場所の状況、工事の規模によって大きく変動します。
| 項目 | 内容 |
| 器具本体 | C級通路誘導灯で1万円前後から、A級避難口誘導灯では数万円以上 |
| 設置工事費 | 1台あたり1.5万円〜3万円程度が目安、配線工事が必要な場合は高くなる |
| 維持管理費 | バッテリー交換(4〜6年ごと)に1台あたり1万円〜2万円、定期点検費用など |
設置基準を満たさない場合の罰則はあるか?
設置基準を遵守しない場合、消防署からの行政指導や改善命令が出されます。
これに従わない場合は、罰金や懲役といった厳しい罰則が科される可能性があります。
しかし、最大のリスクは、火災時に避難の遅れを引き起こし、人命に関わる重大な事態を招くことです。
企業の社会的責任を問われることにも繋がります。
定期点検は義務なのか?
誘導灯は、いざという時に確実に機能するよう、定期的な点検が消防法で義務付けられています。
- 点検頻度については6ヶ月に1回の機器点検、1年に1回の総合点検が基本です。
- 点検内容は外観の確認、機能点検(非常電源への切り替え)、バッテリーの電圧測定など。
これらの点検は専門的な知識を要するため、消防設備士などの有資格者が行う必要があります。
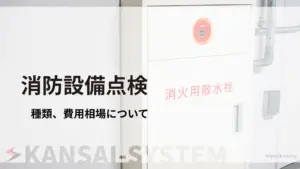
誘導灯の設置・点検は関西システムサポートへご相談ください

ここまで解説してきたように、誘導灯の設置基準は非常に複雑で、専門的な知識が不可欠です。
どの種類の誘導灯を、どこに、何台設置すべきかといった判断は、建物の構造や用途、関連法規を熟知していなければ正しく行えません。
自己判断で設置した結果、基準を満たしていなかったり、消防検査で指摘を受けたりするケースも少なくありません。
無駄なコストやリスクを避けるためにも、誘導灯の設置、交換、点検は、必ず信頼できる専門業者に相談しましょう。
業者を選ぶ際は、消防設備士の有資格者が在籍しているか、施工実績が豊富か、相談や見積もりに丁寧に対応してくれるかなどを確認することをおすすめします。
関西システムサポートは、商業ビル・施設、マンション、工場などで豊富な実績を持つ消防設備工事・点検業務のプロ集団です。
複雑な法令遵守から最適な機器の選定、確実な施工まで、専門家がワンストップでサポートいたします。
まずはお気軽に、無料相談・お見積もりをご利用ください。